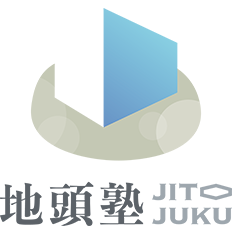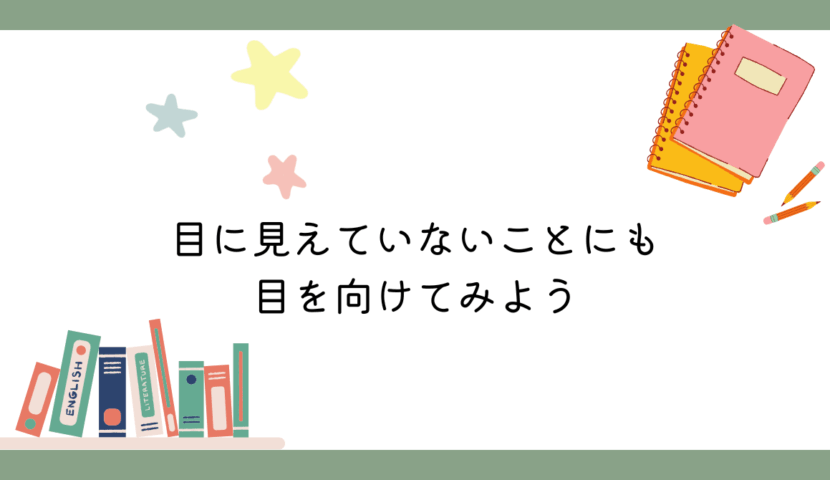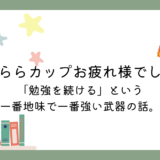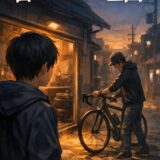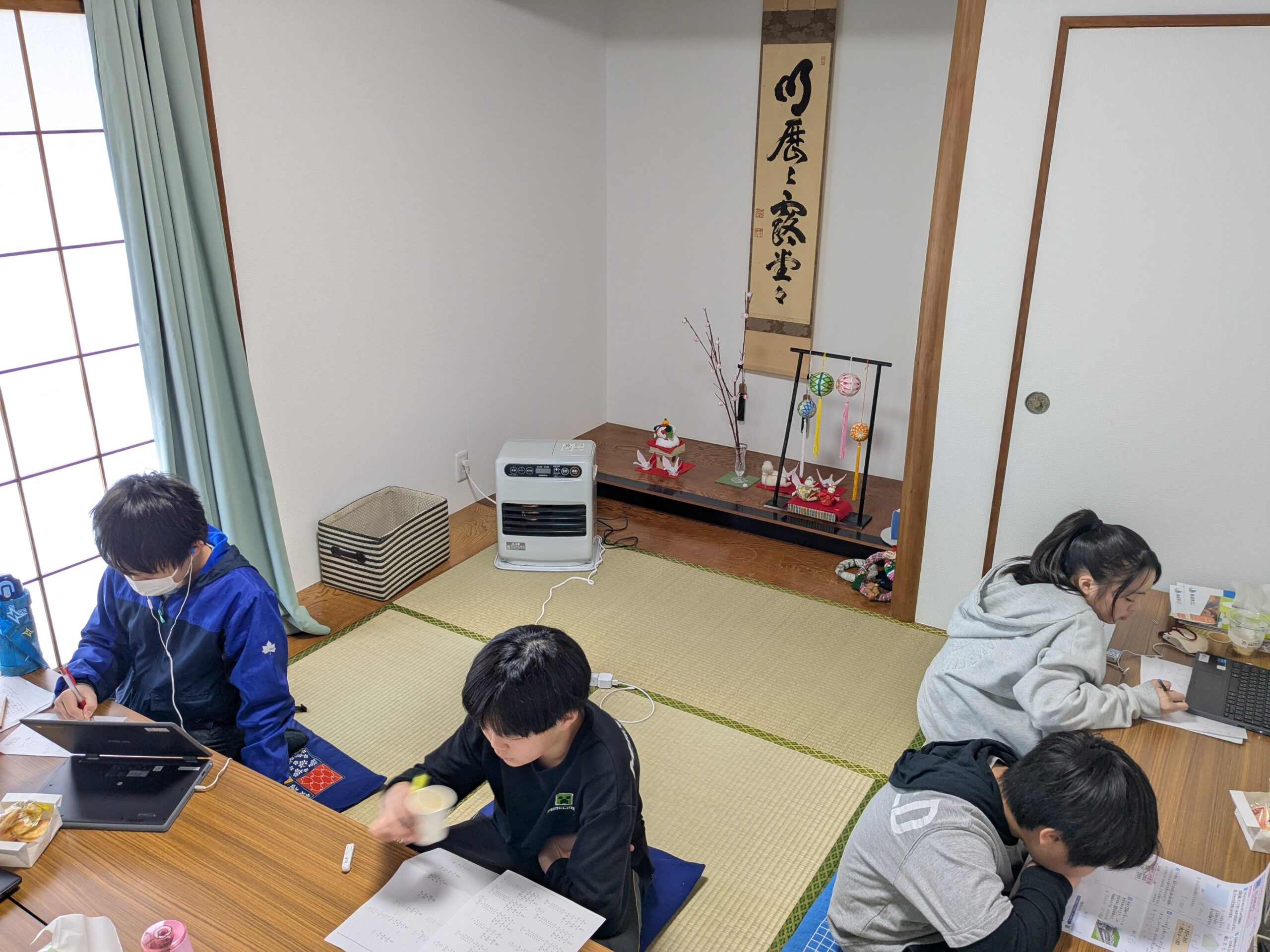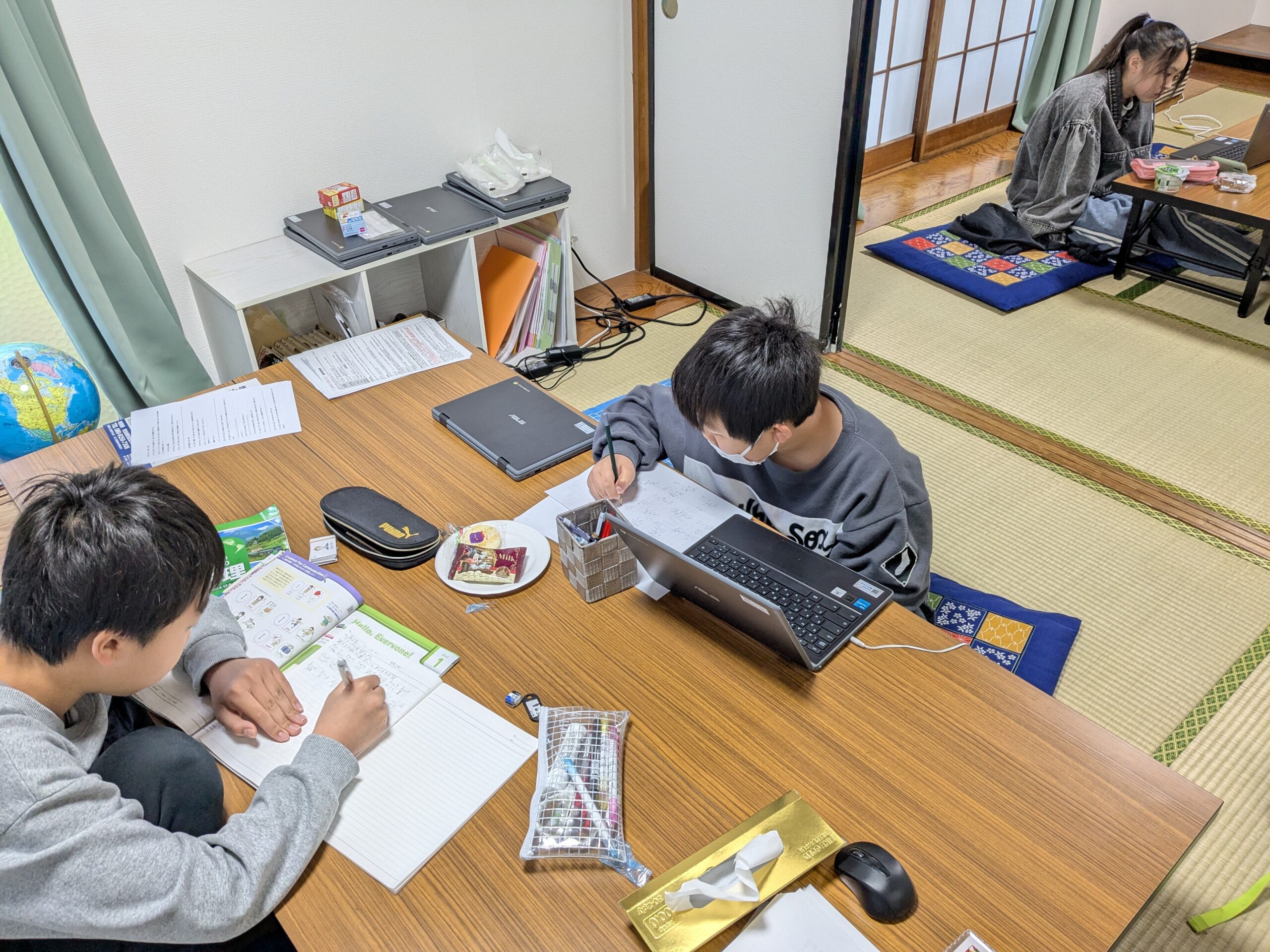「見えていないことにも目を向けてみよう」
〜給食を持ち帰る先生の話から考える〜
先日、ある生徒からこんな相談を受けました。
> 「担任の先生が、給食のご飯やパンをかばんに入れて持ち帰っているらしいんです。」
話を聞くと、その先生のことを普段から良く思っていない生徒が多く、
「ズルい」「ルール違反だ」と感じているようでした。
確かに、給食を持ち帰ることは学校のルール上、認められていません。
その理由は主に次の3つです。
1. 衛生面のリスク — 持ち帰ることで温度管理ができず、食中毒などの危険がある。
2. 公平性の問題 — 一部の人だけが持ち帰ると「不公平だ」と感じる人が出てしまう。
3. 責任の所在 — もし体調不良などが起きた場合、学校や自治体の責任が問われる可能性がある。
だからこそ、ルールとしては「給食は学校で食べる」が正しいのです。
—
けれども、私は相談してくれた生徒に、こう問いかけました。
「見えていないことにも、目を向けて考えてみたかい?」
たとえば——
もしその先生が、こっそり放課後に他の生徒へご飯を渡していたとしたら?
私が知る昔の先生の中には、
家庭内で食事がままならない生徒に、自分の分の給食を毎日こっそり渡していた人もいました。
その先生はルール違反をしていたかもしれませんが、
そこには「助けたい」という強い思いがあったのです。
もちろん、今回の先生が同じ理由かどうかはわかりません。
しかし、私たちが見ているのはいつも「表面」でしかありません。
見えない背景を想像できる人に
世の中には、表向き「よくないこと」に見えても、
そこに思いやりや事情が隠れていることがあります。
「正しい」「間違っている」だけで終わらせず、
「なぜその人はそうしたのか?」と考えることが、
人として大切な“考える力”を育てます。
最後に
今回の話で一番伝えたいのは、
「先生をかばうこと」でも「ルール違反を正当化すること」でもありません。
人や出来事を一面だけで判断しない目を持ってほしいということです。
見えていない事情に心を向けられる人は、
きっと他人にも、自分にも優しくなれます。
「見えていないことにも、目を向けてみよう。」
その一言が、考える力と想像する力を育てていきます。