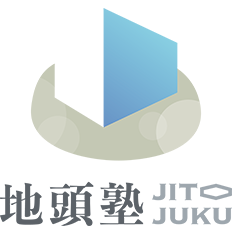守ることと、止めることの間で
健太は、駅前の古い自転車修理店で、週に一度だけ手伝いをしている。
油のにおいと、工具がぶつかる金属音。その静かな空間が、健太は好きだった。
店主の佐藤さんは無口な人で、必要なこと以外はほとんど話さない。
それでも、健太はその沈黙が冷たいとは感じなかった。
むしろ、「余計なことを聞かれない」という安心感があった。
ある日、常連の男性が大切そうにしていたロードバイクが、店から消えた。
シャッターも鍵も、壊された形跡はない。
「変だな……」
佐藤さんはそれだけ言い、しばらく工具を握ったまま動かなかった。
健太は胸の奥が、ざわっとするのを感じた。
その日の夕方、健太は店の裏道で、近所の先輩・亮を見かけた。
亮は、そのロードバイクに乗っていた。
一瞬、頭が真っ白になった。
「……それ、どうしたんですか」
声が少し震えた。
亮はブレーキをかけ、健太を見た。
そして、ほんの一瞬だけ視線を外した。
「借りてるだけだよ。すぐ返すから」
軽く言ったその言葉が、健太の胸に重く落ちた。
「借りる」という言葉が、本当じゃない気がした。
家に帰っても、何も手につかなかった。
もし佐藤さんに話したら、亮はどうなるだろう。
警察、怒鳴られる声、周りの目。
想像するだけで、息が詰まりそうになった。
でも、黙っていたら?
佐藤さんの店が疑われるかもしれない。
あの静かな場所が、壊れてしまうかもしれない。
次の日、佐藤さんはぽつりと言った。
「人ってな、失敗するより、失敗を認めるのが一番怖いんだ」
健太は何も言えなかった。
自分が、逃げている気がしたからだ。
その夜、閉店間際に亮が現れた。
ロードバイクを押しながら、深く、何度も頭を下げていた。
「すみません……」
声は震えていた。
佐藤さんは怒鳴らなかった。
ただ静かに、自転車を受け取り、こう言った。
「返すって決めたなら、それでいい。
でもな、次は“借りる前”に止まれ」
亮は何度もうなずいた。
帰り道、亮は健太に言った。
「お前、言わなかったんだな。助かった。
でもさ……次は、ちゃんと止めてくれ。
止めてくれるやつがいないと、人は簡単に間違う」
健太は何も言えず、ただうなずいた。
黙ることは、優しさかもしれない。
でも、言わないことで守れないものもある。
健太は、自転車のペダルを強く踏みながら思った。
人と向き合うって、きっと怖い。
でも、その怖さから逃げないことが、信頼なんだと。
夜風が冷たかった。
それでも健太の胸の奥には、
前より少しだけ、はっきりした感情が残っていた。